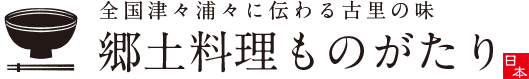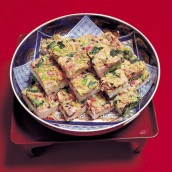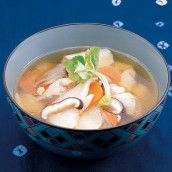徳島県
秋祭りには欠かせない白身魚の押し寿司
ぼうせの姿寿司
秋祭りの時期になるとつくられる押し寿司。魚を7時間以上、酢につけるとやわらかくなり、頭まで食べられる。
徳島県のすしの起源は古く、平安期に朝廷に阿波から魚のすしを贈った記録があるが、現在のような行事食としてつくられ始めたのは19世紀になってから。ぼうぜは、イボダイ、ウボゼ、シズなど、様々な呼び名がある。8〜11月頃に多くとれる白身魚で淡白な味。血合いや骨が少なく、食べやすい。
分量 : 4人前
- ぼうぜ8尾
- 塩小さじ1と1/2
- 酢1.5カップ
- 米280g
- 水1と2/3カップ
- 上白糖大さじ3
- 酢大さじ1と1/3
- ゆず酢大さじ1と1/3
- 塩小さじ1弱
- うまみ調味料0.4g
- 練わさび4g
- 甘酢しょうが32g
- すだち2個
- 1.
- ぼうぜはウロコをとり、頭を左に向ける。
背開きして頭まで開き、気になる場合は腹の骨もとる。 - 2.
- 頭を右にして、中骨にそって切り開く。
- 3.
- 中骨を切り取る。背びれ、胸びれ、尾びれは残す。
(とると形がくずれてしまうため) - 4.
- えら・目をのぞき、血合いものぞいて、流水できれいに洗う。
- 5.
- 塩をふって、30分〜1時間おく。
(一晩ねかすと、さらにおいしい) - 6.
- ぼうぜを酢水で洗い、魚がつかるくらいの酢に30分〜1時間浸ける。
(好みで酢に砂糖を入れても良い) - 7.
- ざるにあげて、酢をきる。
- 8.
- 米を洗って、ざるにあげ、炊飯器に入れて、夏場は30分、冬場は1時間、吸水させてから、炊く。
- 9.
- 上白糖、酢、ゆず酢、食塩、うまみ調味料で合わせ酢をつくり、炊きあがったご飯に混ぜて冷ましておく。
- 10.
- すし飯80gを、ぼうぜの大きさに握り、形を整える。(好みでわさびをつける)
ぼうぜですしを包み込み、上から軽く重石をして、押し寿司にする。
輪切りにしたすだちをのせ、甘酢しょうがを添える。
資料提供 : とくしまの郷土料理